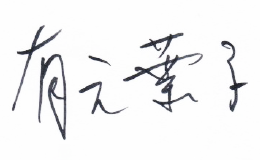鉄フライパンのお手入れ方法

「汚れは溜めない。できるだけ早く落とすのが道具をきれいに長持ちさせる秘訣です。」
(ラバーゼディレクター、有元葉子)
まいにち美味しい料理を作る為に必要なのは、良く手入れされた道具。
良い道具は、大事に末長く使って欲しい。そんな作り手の願いから、これから道具の手入れ方法を紹介していこうと企画しています。少しずつ更新していきますので、どうぞご参考になさってください。
食材のおいしさを引き出すにはやっぱり鉄フライパン!
カリッと焼く、しゃきっと炒めるのは鉄フライパンならではの仕上がりです。
でもこびりついたり、サビたりして使い方が難しそう、と考えている方も多いと思います。
ポイントを抑えれば、ラバーゼ鉄フライパンの使い方は決して難しくありません。
使い方・お手入れ方法を一緒に見て行きましょう。いつもの料理が一味違う仕上がりになりますよ!
■取っ手が短くて鉄でできている理由

オーブンに入れて使えるように取っ手は短く鉄でできています。
みんなの大好きなハンバーグはレンジで表面を焼いた後フライパンごとオーブンに入れるとふっくらジューシーで、一流シェフに負けない仕上がりになりますよ。
鍋つかみを忘れずにお使いくださいね。
■使いはじめは

初めて使う時は中性洗剤でよく洗って下さい。面倒な焼き入れは必要ありません。
■料理の前に

中火で十分に底全体を加熱します。薄煙が上がるくらいまで加熱したら油を底全体にまわし、なじませます。
さあ、これで焼いたり炒めたり美味しいフライパン料理を始めて下さい。
■ラバーゼ鉄フライパンのお手入れ方法

1.お湯とたわしを使って洗います。焼け焦げがついたらしばらく水または湯につけて汚れを落としやすくしてから、たわしでこすります。

2.汚れが取れたら火にかけてから焼きし、水分を飛ばします。熱いうちに油をキッチンペーパーで極薄く伸ばししみ込ませ、余分な油は拭き取りましょう。
この使い方を徹底すればフライパンに油がなじみ、食材のこびり付きやサビを防いてくれるようになります。
日々のお手入れで「フライパンを育てる」気持ちで使っていきましょう。
ここまでは基本の使い方。鉄フライパンを使う時に覚えておいて欲しい事はまだまだたくさんあります。
鉄フライパンを使うときに覚えておいて欲しい事をもっと詳しくお話します。
鉄フライパンは「フライパンを育てる」気持ちで使ってくださいね。
■鉄フライパンの事、もっと詳しく教えて下さい
鉄のフライパンは育てて使ったら一生物。自分だけの宝物になりますよ。

1.何も入れずに先ずしっかり加熱。加熱が足りないと焦げ付きの原因になります。
ガス火は中心に火がないので、フライパンを動かしながら加熱し、中心もしっかり熱しましょう。

2.鉄フライパンは熱してから油を入れて調理します。ここがふっ素樹脂加工のものとは違う所です。必ずこの順番で油をなじませましょう。
また調理中に取っ手が熱くなりますので、必ずミトンなどを使用してヤケドに注意して下さい。
■ラバーゼ鉄フライパンのお手入れ方法

1.洗剤は使わずに洗います。たわしでこすっても落ちない頑固な汚れは、フライパンに水を入れ火にかけてふやかした上で、スチールたわしでこすり落とします。

2.フライパンの裏側はスチールたわしでしっかりとこすり、汚れを落とします。
裏側は熱がダイレクトに伝わり汚れがこびり付きやすいので、磨く様にしてしっかり汚れをこすり落とします。目指すイメージは一流レストランの厨房にぶら下がっている様な、裏までピカピカのフライパンです。

3.水分が残っているとサビの原因になりますので、洗ったら完全に乾くまで加熱しましょう。

4.油をフライパンに塗るときは、油をしみ込ませたキッチンペーパーをトングで挟んで塗るとヤケドを防げます。多すぎるとこびりついてしまうので、余分な油は必ず拭き取りましょう。
■酸化膜が取れた場合は
トマトなどの酸が多く含まれる食材を調理したり、煮物料理をしたりすると表面の酸化膜が取れる事があります。(表面が白っぽくなったりします。)酸化膜が取れた場合でも上記の使い方を徹底すれば全く問題なく、いずれ酸化膜も再生します。
フライパンがだんだん味のある「自分だけのフライパン」になる過程を楽しんで下さい。
有元からの一言「私は白っぽくなっても気にせず、そのまま使っています。使い込んでいい感じになってきますから。」
■サビついてしまった場合は
フライパンに水分が残ったまま放っておいたりするとサビが発生する場合がありますが、サビてもお手入れさえすれば大丈夫。
スチールたわしでサビを全部こすり取って、普段のお手入れの時と同じようにフライパンをから焼きし、温かいうちに油を塗ります。
■こびり付く原因は
フライパンに食材がこびり付く時は、こんな所に気をつけて。
- ※加熱不足
- 鉄フライパンは何も入れない状態でしっかり中心まで加熱しましょう。加熱した後に油をなじませて調理を始めて下さい。加熱と油の順番が逆の方が多い様です。
- ※油分不足
- しっかり油をなじませてから調理を行うとこびり付きにくくなります。フライパンを加熱したら油を適量入れ、しっかり全体になじませてから使いましょう。
- ※汚れ
- フライパンに汚れが残った状態で調理を行うと、その汚れの部分に食材がこびり付きます。使い終わった時にしっかり汚れを落としましょう。最後に手で触って確認すると、汚れがついている所はなめらかではないので、洗い残しがよく分かりますよ。
以上の点に気を付けて、「フライパンを育てる」気持ちで使ってくださいね。

「汚れは溜めない。できるだけ早く落とすのが道具をきれいに長持ちさせる秘訣です。」
(ラバーゼディレクター、有元葉子)
まいにち美味しい料理を作る為に必要なのは、良く手入れされた道具。
良い道具は、大事に末長く使って欲しい。そんな作り手の願いから、これから道具の手入れ方法を紹介していこうと企画しています。少しずつ更新していきますので、どうぞご参考になさってください。
汚れにもサビにも強いステンレスの水切りかご。毎日の洗い物に活躍している事と思います。
だけど、水切りかご自体のお手入れはどうしたらいいんだろう? そんな風にお悩みの方も多いのではないでしょうか。
水切りかごのお手入れ方法を一緒に見て行きましょう!

1.「清潔なふきんを用意します。」
ふきんは台所仕事になくてはならない道具です。清潔なものをたっぷりと用意するのが理想です。

2.「水切りかごを拭きます。クレンザーや研磨剤は使いません。」
手早く丁寧に拭いていきます。ラバーゼの水切りかごはワイヤーが交差しておらず、拭きやすい形状です。

3.「水切りかごの裏側も拭きまます。」
表と同様に手早く丁寧に拭いていきます。水垢は特に裏側にたまりやすいので、しっかりと拭きます。

4.「水切りトレーもしっかり拭きます。」
まず表面を拭きます。そして水垢がこびりつきやすい、トレーの裏側や淵もしっかり拭きましょう。
ラバーゼの水切りトレーの表面はコーティングされているので、カゴ本体同様クレンザーや研磨剤は使わないで下さい。

5.「完成!毎日拭けば、水垢も溜まらず清潔に保てますよ。」
お手入れの方法は至って簡単。毎日拭く事、これだけです。毎日の仕事の終わりにお手入れして、汚れを溜めない事を習慣づけたいものです。
■水垢がこびりついた時は?
水切りかごやトレーに水垢がこびり付いた際は、市販の研磨剤を含まないタイプの水垢落としをお使い下さい。
※水切りトレーは表面がコーティングされているので、研磨剤は使わない様お願いいたします。
ステンレスはなぜサビに強いの?
ラバーゼ水切りかごに使われているステンレスは皆さんもご存じのとおり、サビに強い素材です。
ではステンレスはなぜサビに強いのか? それはステンレスに含まれる“クロム”という物質の働きによるものです。
クロムが空気中の酸素と触れると、表面に不動態皮膜という薄い膜を作ります。 この膜がサビを防いでいるのです。
ラバーゼの水切りかごは、18-8ステンレスというステンレスの中でも特にサビに強い高級素材を使用しています。
お手入れ方法を動画で確認
水切りかごを実際にお手入れしている様子を動画で紹介しています。こちらも参考になさって下さい。
動画の水切りかごは4年間毎日使用しているものです。

「汚れは溜めない。できるだけ早く落とすのが道具をきれいに長持ちさせる秘訣です。」
(ラバーゼディレクター、有元葉子)
まいにち美味しい料理を作る為に必要なのは、良く手入れされた道具。
良い道具は、大事に末長く使って欲しい。そんな作り手の願いから、これから道具の手入れ方法を紹介していこうと企画しています。少しずつ更新していきますので、どうぞご参考になさってください。
まな板はやっぱり木が一番。
木のまな板を大事に使いたいと思っているのに、どうしても黒くなってしまう…。そんな方はもう一度、「木のまな板のお手入れ方法」をおさらいしてみましょう!
まな板を使う前、特に生ものを切る前は必ず、最初にまな板を濡らします。ちょっと水にくぐらして軽く拭けばOK。
まな板をまず水でぬらして拭いてから使うことで匂いがつきにくくなります。

1.タワシを用意します。
「まな板や包丁洗いにはやっぱりタワシ。タワシで木の目に沿ってゴシゴシ洗うとキレイになるの。」
まな板はたわしで洗う、が基本です。タワシはシンクの必需品!

2.「まずは水だけでさっと洗い落とします。いきなりお湯で流しては絶対ダメよ!」
お湯で流すと、お湯の熱で肉や魚のタンパク質が固まってしまい、汚れが取れにくくなってしまうので注意!

3.「たわしとまな板に水を流し、木の目に沿ってゴシゴシ洗っていきます。しっかり、丁寧に。側面や裏も忘れないで洗ってね。」
お目にみえない木のみぞに入り込んだ汚れをかき出すイメージで、水で流しながらこすり洗いします。

4.「手のひらで触って、汚れが残っていないかチェック。匂いも取れているかどうか、嗅いでみてチェックして(これ、大事)。まだ油分が残っているようだったら洗剤を少し付けてゴシゴシ洗います。」
ここでやっと洗剤が登場。
洗剤は必ずしも必要ではない、ということです。
ネギやニンニクなどのにおいの強いものを切るときは、使ったらすぐ水で洗う、を心がけると良いですよ。

5.「お湯を流していきます。洗剤が残らないようによくすすいでね。梅雨時など、気になるときは熱いお湯をさっと流しても良いわね。」
お湯を使うのなら、この段階で初めて使います。

6.「最後に布巾で拭いて、立ててよく乾かしてね。」
陰干しで風にあてて完全に乾かします。ラバーゼの水切りかごの上ならば、まな板を置いた部分も水が溜まることなく、すっきり乾きますよ。
使う前に濡らす、こまめに洗う、最後に洗った後は完全に乾かす。
これを徹底して心がけて、まな板を気持ち良くきれいにしましょう!
ここまではまな板の黒ずみを「防ぐ」お手入れ方法。
うっかり汚れたまな板をそのままにして、まな板が黒ずんでしまった…。
梅雨時にしまっておいたらカビてしまった!
そんな場合はこの方法で。
まずは塩、重曹、酢や、クレンザーでゴシゴシこすってみましょう。
それでもダメならば、薄めた漂白剤につけた布巾をピッタリとかぶせて2〜3時間。
最後は、市販の紙ヤスリ等で表面を削ればある程度は復活します。
でも長時間黒ずみを放って置かれたまな板は、時間とともにカビが芯まで進んでしまうこともあり、復活が難しい場合もあります。
まな板の黒ずみはカビです。黒ずんでしまったらそのままにせず、きちんとお手入れしましょう。
きちんとお手入れして長ーくキレイに使って下さいね!

皆様、こんにちは! 有元です。
『いい道具は料理の腕をそっと上げてくれる』これは私の実感です。
そんな道具ラバーゼがどんな風に生まれたかをお話ししましょう。
料理が大好きだった私は専業主婦だった頃からたくさんの料理を家族や友人たちのために作ってきました。
料理が仕事にもなってきた頃、台所道具を作りましょう、というお話をいただきました。
そこで、それまで使っていたボウルやバットなど基本的な道具について見直すことにしたのです。
キッチンでは鍋釜は最終段階の華やかな存在で、いいものがたくさんありましたが、目立たない下ごしらえの道具は安価に作ることに焦点を置いたもの、デザイン重視で使い勝手無視のものなどがほとんどでした。
下ごしらえの出来不出来で最終の出来上がりには雲泥の差がつきます。
料理の一番大切な段階は表立たない下ごしらえです。そこで、地味な存在だけれど一番大切な下ごしらえの道具をよく考えて作りたい、と思ったのです。
『料理は楽しく楽に、が美味しい料理を作る秘訣』
そのためには使い勝手のいい下ごしらえ用の道具が必要です。ただのボウルやザルに見えて実は隅々まで考え抜かれている、そんな基本的な道具が欲しかったのです。
理由はわからなくても使ってみたらなんだか楽にできる、なんだか料理が楽しくなった、と体がそう感じることが大事なんです。
ラバーゼは使ったらわかる、そういった道具でありたい、と思っています。だから使わないと本当にはわからないのです。
体の動きや感じ方までを考えた設計、長~く使っても大丈夫という堅牢さ、台所には必須の清潔を保ちやすい、見た目はとってもシンプルなのに実にいろいろな使い方ができる、出し入れしやすい、そしてもう一つの要はメイドインジャパンであること、これら全てがラバーゼの基本モットーです。
使うことに徹して考えられた道具は無駄な装飾を削ぎ落としシンプル極まりないデザインとなり、それ自体が美しいです。
これが『用の美』というものです。
メイドインジャパンにこだわったのは、『日本の物作り』を台所で支えたかったから。
決して途絶えさせてはいけない脈々と伝わった伝統、これを私たちの一般家庭で、毎日のご飯作りで支えたかったからです。
煮炊きばかりが料理ではありません。
もしもラバーゼがなかったら、今ほどスピーデイーに、それも楽しく、たくさんの料理を毎日のように作り出すのは難しい。
「ラバーゼがなかったらどうしているかしら、ラバーゼがあるからこんなにできるよね。」といつもスタッフは言っています。
道具を出し、使って、洗って、しまう、そのすべての段階がスムースだと滞りがなくスピーデイーに進みます。
下ごしらえの楽さだけでなく取り出しやすさと片付けやすさも使い勝手の大きな部分を占めています。
ツールを収納するツールスタンドは縦の空間を使う、ということで使い勝手が大幅に良くなりました。
片付けのプロの先生から、ラバーゼツールスタンドは本当に優れもの、とお墨付きも頂きました。
サイズを限定しているのも取り出しと収納の両方を考えた為です。
また、どうして入れ子にして沢山のサイズを作らないのですか?と聞かれることがあります。
それは以前に沢山の入れ子の道具を持っていてその使いにくさを身をもって知っていたから。
だから本当に使えるサイズに限定しています。
ラバーゼでは試作と試用を徹底しています。
実際にある程度の期間使ってみないと、本当に使いやすいかどうかはわかりません。
試用しては修正と試作を繰り返すので開発期間に2年、3年を費やすこともザラではありません。
使う人の立場に立つことが最優先なので、妥協はしないことを貫いています。
la baseとは基本という意味です。イタリアにご縁があった私だったので、この基本的な道具をイタリア語の『la base』と名付けました。
これからますます長寿社会となりますが、なんといっても健康が第一。
健康のためには自分で自分のご飯を作る、これが基本。
ご飯は楽に、楽しく作る、これが長く続く秘訣です。
台所の縁の下の力持ちラバーゼが皆様のお台所でお役に立てばこれほど嬉しいことはありません。